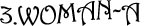
ヴィクターは一旦決めたらやっちまう男だったんで、その五ヶ月後、結婚しました。相手はちょうどその頃付き合ってたコニーってかわいい女の子でした。 とてもいい結婚式でしたよ。彼の親しい友人と相手の身内だけが集まってね、派手でも地味でもなく、趣味のいい、気持ちのいい式でした。 いや、さすがにあたしもこんな時までポケットの中にお邪魔してるのが心苦しかったもんで、昼の間にちょんちょんとラリー君のズボンのポケットに移動して、そっから胸ポケットに移動して、コサージュの間から目と鼻先だけ出しておとなしくしてやしたよ。あたしにだって節度はあるんで。節度は。 しかし人間ってのはどうしてああ酒を飲みますかな。あたしは体がちっさいせいか、実にあれに弱くてね。匂いを嗅ぐだけで酔っちうまう。 だからラリー君に取り付いたのは失敗だったかもしれませんや。この男、パーティが始まるや深夜までぐんぐん休みなしに飲みやがって、辺りはアルコールの霧。あたしゃ半死半生でした。 そんな地獄の馬車状態で聞いた話です。 「ヴィクターの姉君がおめでただってのは本当かい」 これは例の作曲家君の声でした。 「…どうだかな」 物憂げ(あんだけ飲めば誰だってそうなりまさあ!)に答えるこれがラリー。 「どうだかなって、それで姉君欠席なんだろ。船旅を医者に止められたって聞いたぜ」 「時にレオ、ナポレオンのかみさんがイタリアに行きたくなくて使った口実知ってるかい。妊娠と流産だよ」 「…なんだって?」 「女はいつだってそういう手を使うってことさ…。ウチのは本当だったけど」 うっぷす。あたしも鵜呑みにしてたわけじゃなかったんで。うおっぷ。 そもそも姉君は反対だったんですよ。人気絶頂の今、結婚なんかして女性ファンを軒並み失うのは得策じゃないなんて手紙を寄越してね。正しい意見かもしれませんが、お前が言うなって感じですな。 姉弟の間に何度か緊張した、それでいて取り澄ました手紙が往復して、姉貴からの最後の手紙の主旨は「出席できません」でした。 オ医者様カラトメラレタカラ。 しかし、両親が亡くなっていたその時、移民の子であるヴィクターの家族なんて、姉貴の他にはいねえんですよ。たった一人の身内も出席しねえなんて、やっぱり困るわけですが、ウイーそこは人徳ってのかな。 特にこのラリー君、花嫁のご両親にも花嫁にも、当り障りなく事情を話して、式の前に承知しててもらったんで。 それに他のお仲間連も手前が忙しい中、めいめいきちんと都合をつけて式にやってきてね。花嫁側のお友達が羨むほどのお歴々で、ヴィクターの面子を救ってやりました。 思えばヴィクターがアリスに肘鉄を食らわしたのは、これが最初だったかもしれねえです。もうあんたの加護なんぞ必要ないんだとはっきり言ってやったんですからな。 これ以後、ヴィクターと姉貴の間はよそよそしくなりました。クリスマスカードや誕生日カードを送り合うだけの、遠い親戚みたいな付き合いになって。 ただし姉貴の方も大したもんで、去り際の一撃みたいなのがありましたよ。 式の翌朝、腹ぼての女房が差し出したコーヒーを飲みながら新聞を開いたラリー君、絶句。ガウンの肩にいたあたしも絶句。 なんと芸能欄に「英国のアリス、弟の結婚について語る!」てな記事がばーんと出てんです。コニーの希望で式は一切プレス排除でやりましたから、姉貴のもたらした情報は大きな扱いになってました。 喉から手が出るほど記事が欲しい新聞側が持ちかけたのか、それともアリスの方から電話をしたのか定かじゃあありませんでしたが…。 ともあれ、ここで騒いだら思う壺だということは明白でしたからね。ヴィクターもラリーと笑って済ますことにしましたが、ちょっと胸の中じゃ心臓ひっくり返ってたんじゃねえかなあ。 全く。放っておいたらどこまでやるやら分かったもんじゃない。 しかしそういう些細な出来事を別にすれば、結婚してからの数年はホント、ヴィクターの黄金期に相応しい充実ぶりでした。結婚したって、三十を越したって、奴の人気は衰えねぇんで。そういうものに立った人気じゃねえんで。崩そうにも隙の無い、何十時間ものリハーサルに支えられた人気だったんですからね…。 その後彼はカラーもステレオも、あのテレヴィジョンさえ乗り切った。それも全て道理です。とにかくヴィクターはセレブ云々とか言う前に、鉄壁なほどダンサーだったンです。 映画会社ももうヴィクターを疑おうなんて思いませんでしたよ。上品で、明るく楽しく、いつだって約束じみて質が下がらない。ヴィクターと彼の出る映画は、その頃にゃ会社の大看板になってました。 …が。あんましフツーに順調なんで、あたしゃかえって退屈でした。ま、その辺が鬼の鬼たるとこですがね。 あたしは福の神様とは違うんで、幸には興味が薄くてね。もうそろそろこいつから離れて、劇場に帰ろうかなーって気になってやした。 ホリウッドの浪費と絢爛も見飽きた。また小汚い劇場の猫走りから、芸をするガキどもを眺めるのも悪くねぇやなあ…。 なんて考えてた矢先です。 作曲家のレオ君が死にやした。 あたしゃ人間の心臓が止まる仕組みなんてよく存じませんが、いくらなんでも三十七年はちっと短いでしょ。 後ろ六年はずっとヴィクターと一緒でした。ヴィクターはホントにしょげちまって、葬儀の最中も終わったあとも、長らく一言もありませんでしたよ。 なんだか厭だな。とあたしは思いました。おでこのあたりがいやーな感じにひりひりしてたんで。 何か今年はヴィクターにとって悪い年になるんじゃないか。そんな胸騒ぎがありやした。 ―――――鬼の勘は外れねえもんで。 厭な事がありました。 コニーが死んだんです。 あたしゃやっぱり、何でだか知りません。でもある日調子が悪いと行って病院に行ったら、それっきり帰って来ませんでした。二ヶ月入院生活が続いて、五月の頭。一番いい季節に死にやした。 何ででしょう。コニーは何も悪い事なんかしてませんでしたぜ。ヴィクターも。真面目に懸命に芸に努めて、何万人もの客を楽しませてきましたぜ。 だけどそういうのと、…寿命云々とは、関係ねぇんですな。我らがご主人が下す決断は、問答無用なんですな。 まさに前触れもねえ、冗談みたいな死に方でした。一同は声を失いましたよ。 コニーはおっとりして気のいいだけが取り得の、どおってことのねぇ女でした。だのにそれが余計に暗くって、…そうか、と。 彼女も結局、いなくなってみないとその価値が見えないタイプの人間だったってことですな。彼女は彼に、よく似ていました。 悪い風が吹いてました。 ヴィクターは丁度、映画の撮影の最中だったんですが、さすがに葬儀の後はまる一日飯も食わず、部屋から出てこられませんでしたよ。 しかし撮影をいつまでも中断しておくわけには行きません。止めるなら止めると決めないと、日々だけで経費は流れていくんでね。 ヴィクターの家の客間にはすぐと、青い顔をしたプロデューサや、映画会社の重役や、或いは誰かに懇願されたような友人たちが、暗い雰囲気で留め置かれるようになりました。 あたしは気が滅入って仕方が無いんで、ヴィクターの側から離れて、廊下の隅の暗がりで横になって、肘を付いておりやした…。 さァ…ヴィクターの再起にどれくらいかかるもんか。人間の心は脆いもんで。 一ヶ月か、二ヶ月か、半年か。 引退したいなんて言ってたこともあるから、もう辞めちまうかもしれねえなあ…。 仕方がねえ。そういうのは仕方がねえ。人間は油さしゃ動き出す自動車とは違うんで。無理矢理走らせると潰れちまうこともありやす。 子供を亡くしてアル中になった役者。亭主亡くして声が出なくなった歌手。あたしの知ってる可哀相な連中のことが色々思い出されました。 どうなることやら…。 そう思った時です。あたしのかわいい鼻が馴染みの無い香水の匂いに、ひくひくっとしました。 なんだこりゃ。どきつい花の香り。一体誰だ? 客間を通り過ぎて一直線に、こっちに向かってくる。 顔を上げたあたしはそん時、まさかと思いましたよ。 まさか…! こんな時にあんた。 ………アリス………。 アリスは、とても四十過ぎとは思えねぇような美貌で、思いっきり清楚な格好をして、悲劇の大女優みたいに廊下を歩いて来やしたよ。 ヴィクターの部屋の前に立つと、扉をノックして、入りますよと言うなり開けました。あたしはきっと、客間の連中と同じ様に、唖然としてそのつむじ風を見送りました。 あたしの思ってるようなことが起きてなければいいと思いました。もっといい解釈をしようともがきました。 アリスは、弟が心配で、心配でやって来たんだ。今までの屈託を全て忘れて、心配でやって来たんだ。 そう思おうとしましたよ! きっつい香水の匂いに、吐きそうになって顔をしかめながら。 二十分ほどでしたか…。石の彫刻みてぇに役立たずになってたあたしらの耳に、扉の開く音がしました。 最初にアリスが。その後ろから青白い顔のヴィクターが出てきましたよ。 会社の連中が…、駆け寄って彼の手を握っている間に、プロデューサが電話を掛けに飛びだしていきました。撮影は続行だ。機材をバラすな。 ヴィクターは心配をかけてすまなかった。やるよ、と話してました。客間にいた全員の目が、アリスに吸い付いているのが分かりやした。人前で姉の面子を潰すことが出来ねぇ弟の立場なんか、誰も考えちゃいませんでした。 あたしは正直、撮影現場を見たくなくて、ヴィクターが出かけていく車の音を廊下の暗がりの中で背中に聞いてやした。 その晩は夢の中にまでその女の匂いがしましたよ。 一旦撮影を再開したら、後はもう普段どおりでした。あたしも二日目からはくっついて出ましたが、ヴィクターが以前と変わらずとびっきり粋に、思いっきり愉快に恋愛コメディを演じるものだから、スタッフ達の顔つきなんて既に神々しいものに対するそれになってました。こっそり涙ぐんでる女の子もいましたね…。みんながヴィクターのプロ意識の強さに、感嘆の眼差しを注いでいました。 でもあたしは…。あたしは一人でヘンでした。 あたしはちょっとぞっとして、ヴィクターを気持ち悪いと思ったんです。 や、最初は考えようとしたんです。ヴィクターは今、無理矢理演技してあんなに明るく振舞ってるんだって。姉貴の意地に強要されてるんだってね。 でも何だか、今日もまるでお手玉みたいに空気を切って、体を自在に動かしている彼を見ているうちに、とてもそれだけだとは思えなくなってきたんで。 だって変でやすよ…。こんな時にも飛べるなんて。…普通じゃねぇです。声が出なくなって落ちぶれる歌手の方が、どれほど人間らしいか分かりゃあしない。 …あたしはそん時、ヴィクターに踊って欲しくなかったんです。歩くみたいにステップを踏みこなして欲しくなかった。こんな時に、空を飛んで欲しくない。 どうして、そんなに生き生きとしているのか。 まるで、こっちが自分の本当で、 妻が死んだことなんて…。 せめて転倒の一つくらいしておくれ。 無理に演じているというのなら、せめて。 …祈るようにそんなこと考えました。 どうしてなかなか、鬼の気持ちも複雑ですよ。 ちっと草臥れて、あたしゃ楽屋に引き上げました。戸棚の上に寝そべったが最後、ぐーっといつの間にか寝込んじまって、…どれくらい経った後だったのか、ふと人の話し声で目が醒めました。 「もう充分だろぅ…。帰ってくれないか」 やや、この声はラリー君です。今日は撮影があって来られなかったはず。けりをつけて来たんでしょうか。 ずるずるとはいつくばって戸棚の端からひょいと顔を出すと、確かに彼で、手には今日の新聞を広げてました。 反対側、鏡の前にはアリス姉貴。弟の椅子に座って、少し俯いて、また少し笑ってました。 「まあラリー。奥さんとかわいいお子さんを紹介してくれないの?」 「…よしてくれ」 ラリーの声は、吐き捨てる様でした。さすがに場数踏んでるだけありますな。 「今朝の新聞はどこも君の美談で一杯だ。こんだけ写真に撮られりゃ満足だろう。もうロンドンに帰るんだ。 …僕もヴィクターも、君の虚栄心はよく知ってる。連中のようには踊らされん」 「…随分生意気な口をきくようになったのね、ラリー。私の接吻を求めてバカみたいに泣いていた晩もあるくせに」 「…君にとっては価値の無い話だろう。君に必要なのは誠意じゃなくて地位なんだから。 君は自分の地位の為に華々しく僕らを棄てた、そういう女だ」 「そうね。私の夫は男爵。あなたなんて、吹けば飛ぶような薄汚い芸人だわ。ウェイトレスとの間にうじゃうじゃ子供を生んで…。 ヴィクターも同じね。もっともあの貧相なお嬢ちゃんはそれすら出来ないで、見事に死んじゃったけど」 「………」 『その時、姉は優しく言った。』 つまんねえ新聞記事が畳まれて、ごみ箱へ投げ込まれやした。 「帰りたまえ、今すぐ。これ以上コニーとヴィクターを侮辱する気なら、僕は紳士であることを止める。 君が今ここにいて、ヴィクターの椅子に座っていること自体がコニーに対する許しがたい冒涜なんだ」 珍しく格好のいい捨て台詞で部屋から出て行こうとしたラリーでしたが、アリスの呟きで、その動きが止まりやした。 「バチが当たったのよ」 「………なに?」 アリスはラリーの方なんか見てませんでした。うっとりと鏡を見てました。頬杖をついて、かつて人々の熱狂を煽った横顔で、言うんです。 「……私の言う事を聞かないで勝手な真似をするから…、バチがあたったのよ…。いい気味だわ」 一体なんで、美しい顔なんてものがあるんでしょうな。何のためにそんなものが 「――――地獄へ落ちろ…!!」 扉が閉まった音もまるで聞こえないって風に、アリスは優雅な様子でしばらく、鏡の前のメイク道具をおもちゃにしてました。 妻が死んだばかりの男の地味な控え室で、彼女が動くたびに香りが空気に散り、何かレースに囲まれた別の生き物がもぞもぞしているような、一種異様な感じがしました。 あたしはどうやら気付いたんですが、その匂いが嫌いでね。退散しようかな、と思った矢先、女が独り言を言いやした。 「…どいつもこいつも…、勝手な事ばかり…」 どことなく虚ろな目が、鏡面をぼんやり眺めてました。 「…あたしを苛めてれば満足なんだわ…」 それを聞いた時、あたしはほーっと嘆息をつきたくなりましたよ。もうたくさんだ。たくさんだから、ここから出よう。そう思って戸棚から降りようとした時でした。 「そうでしょ、小鬼さん―――」 どきぃッッ!! としましたね。 …え?! 何? あたし? あたしに?!! そりゃパニックですよ。…だってあたしの存在が分かるような奴は、百年に一度といねえんで。 振り向いたら鏡越しに女の両目がじいっとこちらを睨んでやがって、あたしゃ恐ろしくて思わず腰がへなへなっとなりやした。 「…何を今更あの子達はきーきー喚くのかしら…。あんなになってもまだ知らないのね…。図体だけでかくなって、オツムの中はまだ憐れな芸人そのものなのよ…。あなたは知ってるんでしょ…?」 あ、ああああたしが、あたしが、 何を知ってるって…? 「力を持たない連中がどれだけ憐れなものかって…。どれだけつまんないものかって…。 そうか…。あなたの小屋はいい小屋だったから…、あなたは直接見てないかもしれないのね…。 でもね…、小鬼さん。知ってるでしょ。世の中には相手の立場が弱いと見るや、いくらでもつけ込んで来る連中がいるのよ…。通りにも、劇場にも、たくさん…」 何がおかしいのか、アリスは赤い唇でくつくつと笑いやした。 「ヴィクターは忘れても、あたしは忘れないわ…。あたし達が力が無くて惨めだった頃、あたしがさせられたことについて…。 ホントに…男って分かってないわ…。自分の体を無理矢理触られるのがどれほど嫌か。他人のものがあたしの中にねじ込まれるのがどれだけ嫌か…」 ああ…アリス…。 アリス…、お願いだから…。 「ヴィクターが役立たずで何も分かっていなかった時…、公演のためにあたしは盾にされたのよ…。だから今更何を言うの…。 金があれば見くびられないわ…。名前があればなぶられないで済む…。新聞に名前が載れば安心だわ…。あたしはもう、何も出来ない力のない小娘ではない!! 棄てないわ…、この場所を…。絶対に棄てないわ…。そこらのバカな芸人連中に嫌われたってそれが何なの…。好きにするがいい。その代わりあいつらが死んだら、貧相な墓に唾を吐きかけてやる…。この世の中の事を一番わかっているのはあたしなんだ…! 満足なの。愉快なの。あたしはもう…。 あたしはもう…」 アリス、止めて。あたしには分かるんだ。 撮影を終えたヴィクターが扉の外に立って、話を聞いてる。 「あんな卑小な奴らとは違うんだ…!」 …気配が、足音も立てずに、廊下を退いていきやした。あたしは、耐え切れなくなって楽屋を逃げ出しました。 アリスには気の毒だし、アリスが悪いわけじゃあねえんでしょう。 それでも誰も、彼女のいる部屋には一緒に住めねぇでしょう。 彼女はイギリスの、鈍感野郎のお屋敷に帰るべきです。 |
| << back | [ topへ戻る ] | next >> |